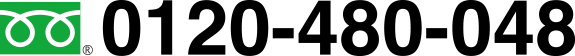お寺の檀家をやめるにあたり(離檀をするにあたり)、離壇料はいくら払えばいいのでしょうか?
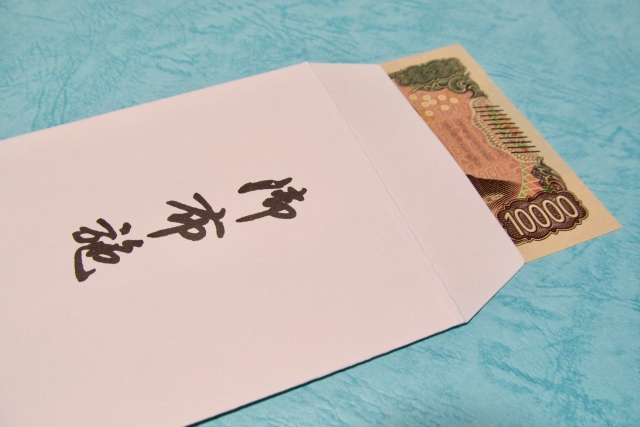
離檀料の相場と支払いについて
離檀料(りだんりょう)は、お寺の檀家(だんか)をやめる際に求められる費用ですが、法律上支払い義務はありません。ただし、長年お世話になったお寺への感謝の気持ちとして、お布施の形で渡すのが一般的です。
離檀料の相場
離檀料の相場は3万円~30万円程度と幅広いですが、以下の要因によって変動します。
-
お寺との関係の深さ
- 長年檀家として支援していた場合、高めの金額を求められることがある。
- 代々続くお墓の場合、特に高額を請求されることも。
-
お墓の規模や場所
- 大きなお墓や管理費を長期間払っていた場合、お寺が収入減を理由に高めの離檀料を求めることがある。
-
お寺の方針
- 離檀料を求めないお寺もあれば、強く求めるお寺もある。
- 地域差があり、特に都市部より地方のお寺の方が離檀料を請求されるケースが多い。
離檀に関するトラブル事例
1. 高額な離檀料を請求されたケース
事例:
ある家族が墓じまいをするために離檀を申し出たところ、「50万円を支払わなければ離檀は認めない」と言われた。お寺側は「先祖代々の供養を続けてきたのだから、それに見合う金額が必要」と主張。
対処:
- 相場より明らかに高額な場合は、支払い義務がないことを伝え、交渉する。
- 地方自治体や消費者センターに相談すると、お寺側が態度を軟化させる場合がある。
- 代わりにお布施として3万~10万円程度を支払って解決することも。
2. 離檀を拒否されるケース
事例:
檀家をやめたいと申し出たが、「檀家をやめることはできない」「墓を撤去する許可を出さない」と言われた。
対処:
- お寺には檀家を強制する権利はないため、改葬許可証を市区町村に申請し、手続きを進める。
- 交渉が難航する場合は、弁護士に相談する。
3. 遺骨を引き渡してもらえないケース
事例:
墓じまいをしようとした際に「離檀料を支払わない限り、遺骨は渡せない」とお寺に言われた。
対処:
- 遺骨は遺族の所有物であり、お寺が引き渡しを拒否する権利はない。
- 改葬許可証を役所に申請し、法的に進める。
- 消費者センターや弁護士を通じて対処する。
4. お布施の要求がエスカレートするケース
事例:
離檀料として「お気持ちで」と言われ、10万円を包んだが、「これでは少ない」と追加を要求された。
対処:
- 明確な金額を決めて、追加請求に応じない姿勢を取る。
- 相場(3万~10万円程度)を参考に、事前に決めた額を渡す。
離檀トラブルを防ぐためのポイント
-
お寺と冷静に話し合う
- 「金銭的に余裕がない」などの理由を伝え、柔軟な対応を求める。
-
複数の相場情報を確認する
- 他の檀家や石材店などに相談し、適正な金額を把握する。
-
法的機関や消費者センターに相談する
- 強制的に高額な離檀料を要求された場合は、消費生活センターや弁護士に相談する。
-
適切なお布施を用意する
- 相場(3万~10万円程度)を包み、「お世話になりました」と伝えることで、円満に離檀できるケースが多い。
結論:離檀料は法的義務なし、慎重に交渉を
- 支払いは義務ではないが、円満な関係を築くためにお布施を渡すのが無難。
- 高額請求や不当な要求には毅然と対応し、法的機関を活用する。
- 事前に情報を集め、相場を理解してから交渉を進めることが重要。
離檀は慎重に進める必要がありますが、適切な手順を踏めばスムーズに進められます。