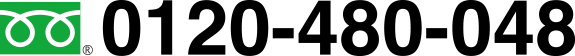墓じまい後の墓石はどのように処理されるか。

墓じまい後の墓石の処分方法を詳しく解説!
墓じまいを行った後、取り出した遺骨は「改葬」や「永代供養」などの方法で供養されますが、墓石自体はどのように処分されるのか?
墓石の処分方法は意外と知られていませんが、実は以下のような方法があり、それぞれに特徴があります。
1. 墓石の処分方法(一般的な流れ)
① 石材店による撤去・処分
墓じまいを行う際、ほとんどの場合は石材店に依頼し、墓石を撤去・処分します。
- 墓石を重機で取り外し、砕石(さいせき)処理を行う。
- 処分場へ運搬し、砕石や埋め立て資材としてリサイクルされることが多い。
📌 ポイント
✅ 墓石は自治体のゴミとしては出せないため、専門業者に依頼する必要がある。
② 寺院や霊園の敷地内で「供養塔」や「墓石供養所」に移す
寺院や霊園によっては、撤去した墓石を供養塔や墓石供養所に安置する場合があります。
- 「お墓を完全になくすのは抵抗がある」という人向けの選択肢。
- 石材を再利用することもある。
📌 ポイント
✅ お寺や霊園に相談すれば、供養塔に移すことができる可能性がある。
✅ 遺族の希望で供養塔へ移すことも可能。
③ 墓石を自宅の敷地に移動する
- 墓石の一部を庭などに移動し、記念碑や供養のシンボルとして活用する方法。
- 「ご先祖の記念として残したい」という場合に選ばれることがある。
📌 ポイント
✅ 寺院や墓地管理者に事前に相談が必要。
✅ 処分ではなく、供養の一環として検討されることが多い。
④ 墓石を寄付・リサイクルする
墓石は「御影石(みかげいし)」などの高価な石材で作られているため、リサイクルされることもあります。
- 一部の石材店では、古い墓石を再加工し、新しい墓石や石材製品として再利用する。
- 学校や公園の舗装材として使われることもある。
📌 ポイント
✅ 墓石の形を残したまま寄付できる場所は少ない。
✅ 再利用する場合も、元の文字は削られる。
⑤ 海や山に「自然石」として還す(自然供養)
墓石を処分せず、川や海、山などに石として戻す方法もあります(ただし、自治体の許可が必要)。
- 山や川に戻すことで、自然に還す供養の方法とすることもある。
- 自治体のルールや環境への影響を考慮する必要がある。
📌 ポイント
✅ 自治体によっては違法になる場合があるため、事前に確認が必要。
✅ 山や川に戻す場合、宗教的な儀式を行うことが多い。
2. 墓石の処分費用
墓石の処分には撤去費用+運搬費+処理費がかかります。
一般的な費用相場は以下の通り。
墓石の撤去・処分費用の相場
| 墓石の大きさ | 費用の目安(1基あたり) |
|---|---|
| 小さい墓石(0.5㎡程度) | 10万円~20万円 |
| 中くらいの墓石(1㎡程度) | 20万円~30万円 |
| 大きな墓石(2㎡以上) | 30万円~50万円 |
📌 ポイント
✅ 墓地の立地(山間部や狭い場所)によっては、費用が高くなることがある。
✅ 墓石が大きいと、運搬や処理のコストも上がる。
✅ 事前に複数の業者から見積もりを取るとよい。
3. 墓石処分の際の注意点
① 勝手に処分しない!
- 墓石は勝手に撤去や廃棄してはいけない。
- 墓地の管理者(お寺や霊園)に相談し、適切な方法で進める。
② 閉眼供養(魂抜き)を行う
- 墓石を処分する前に、「閉眼供養(へいがんくよう)」を行い、墓石から魂を抜く。
- 宗派によって供養の方法が異なるため、お寺や僧侶に相談するのがベスト。
③ 親族と相談する
- 墓じまいは家族や親族との意見が分かれることがある。
- 「墓石をどうするか?」について、事前に話し合っておくことが重要。
4. 墓石の処分でよくある質問
Q1. 墓石を撤去しないでそのまま放置してもいい?
➡ NG!
- 墓地は「永代使用権」で借りているため、墓じまいしない限り管理費がかかる。
- 放置すると、墓地の管理者によって強制撤去される場合がある。
Q2. 墓石を別の場所に移動することはできる?
➡ 可能。
- 自宅に移す場合、自治体の許可は不要。
- 墓石の一部を記念碑として残す人もいる。
Q3. どの業者に依頼すればいい?
➡ 石材店 or 墓地の指定業者
- 墓地の管理者に「指定業者」がいるか確認。
- 指定業者がいない場合、複数の石材店から見積もりを取る。
5. まとめ
✅ 墓じまい後の墓石は、基本的に石材店が撤去・処分する。
✅ 処分方法は「砕石処理」「供養塔への移動」「寄付・リサイクル」「自宅供養」などがある。
✅ 墓石の処分には10万~50万円ほどかかる。
✅ 処分前に「閉眼供養(魂抜き)」を行い、家族とよく相談することが大切。
✅ 無断で撤去・放置すると、管理者から強制撤去される可能性もある。
墓石の処分は慎重に進める必要があります。家族の意向や供養の形を考えながら、最適な方法を選びましょう!